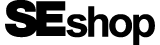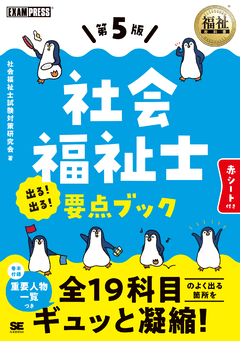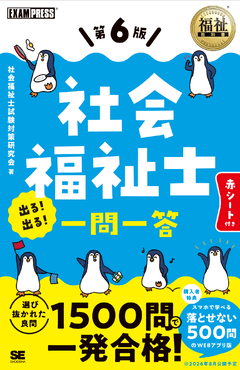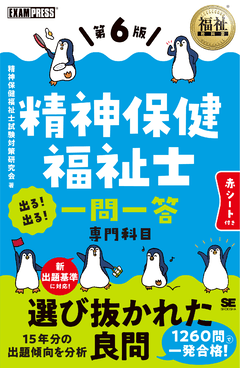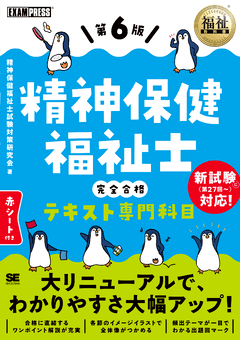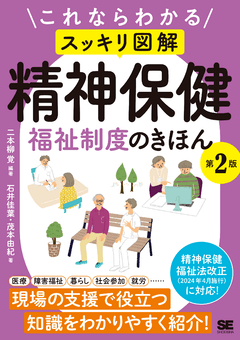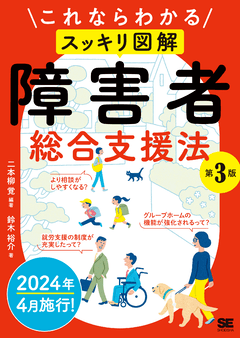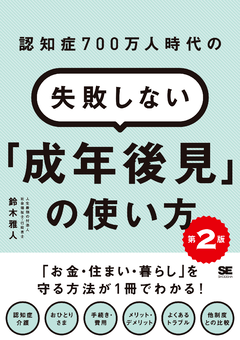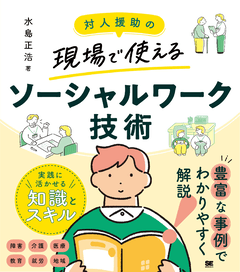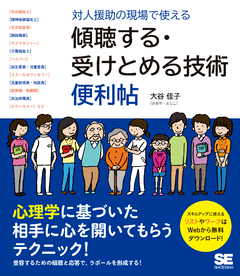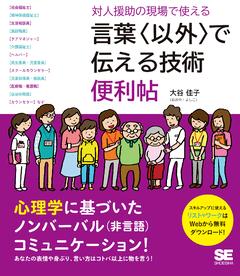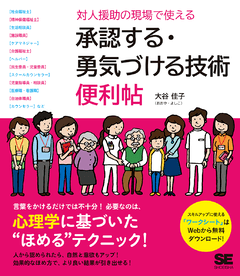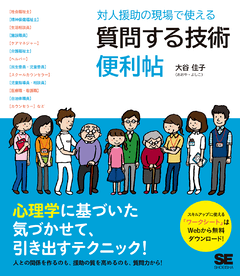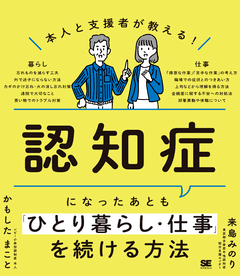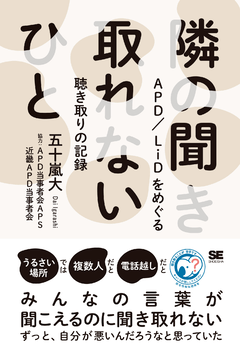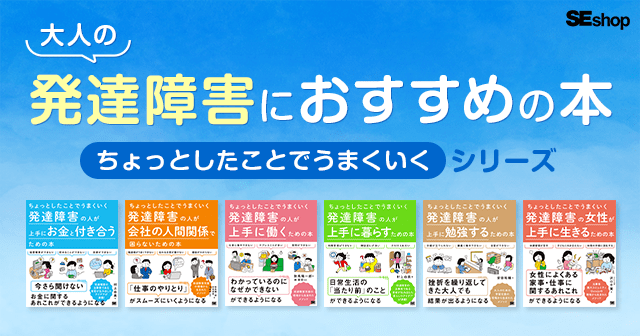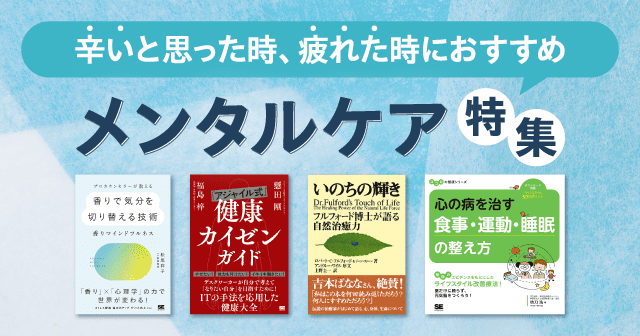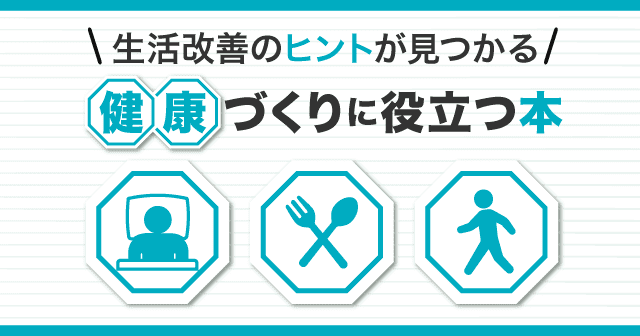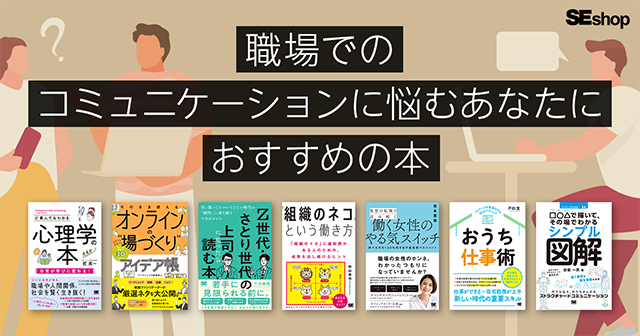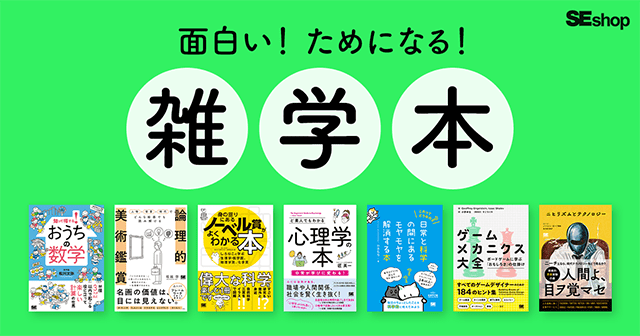社会福祉士・精神保健福祉士になろう!ソーシャルワーカーにおすすめの本
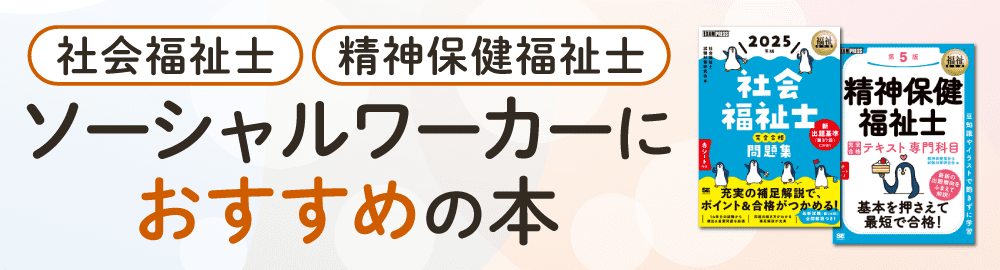
福祉施設において重要な役割を持つ社会福祉士と精神保健福祉士。これらを名乗るには国家資格が必要であり、試験は科目数が多く難易度の高いものになっています。また、ソーシャルワーカーとして働く現場は多岐にわたり、施設の種類によって求められる役割も異なります。
今回は、社会福祉士や精神保健福祉士、福祉の現場で働くソーシャルワーカーに役立つ書籍をまとめました。試験対策の参考書はもちろん、現場で役立つ対人援助の技術、活用できる法律の知識など、支援者としての幅が広がる本をご紹介。
今後ますますニーズの高まる福祉職。知識とスキルを身に付けてワンランク上の支援者になってみませんか?
【こんな人におすすめ】
- 社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取りたい人
- 福祉の現場で働くソーシャルワーカー
- しっかりとした対人援助の技術を身に付けたい人
社会福祉士・試験対策
『福祉教科書 社会福祉士 完全合格問題集 2026年版』
『福祉教科書 社会福祉士 出る!出る!要点ブック 第5版』
『福祉教科書 社会福祉士 出る!出る!一問一答 第6版』
精神保健福祉士・試験対策
『福祉教科書 精神保健福祉士 出る!出る!一問一答 専門科目 第6版』
『福祉教科書 精神保健福祉士 完全合格テキスト 専門科目 第6版』
福祉現場で役立つ法律
『これならわかる〈スッキリ図解〉精神保健福祉制度のきほん 第2版』
精神科領域の全体像をつかんで現場の支援に活かす!
精神疾患・精神障害の種類や症状は患者さんごとに多種多様。多くの場合、治療は長期に及ぶため、症状と付き合いながら仕事をしたり、いくつもの課題を抱えながら生活している方が少なくありません。そのため、薬や心理療法などの医療的ケアとともに、様々な支援制度やサービスを患者さんの状況に合わせて活用することが重要です。
本書は、主に精神科にかかわる専門職や患者さんを支える家族などに向けて、精神保健福祉に関する制度・サービスをわかりやすく整理して紹介。精神疾患や精神障害の基礎知識もまとめており、初めて精神科に勤務する人や学生にも入門書としておすすめ。病院以外の場所で、課題を抱えて生活する人を支援する上でも役立ちます。
『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第3版』
2024年4月、改正障害者総合支援法が施行。何がどう見直され、何が変わるのか?
2024年4月改正の「障害者総合支援法」では、グループホームの定義が変わったり、「就労選択支援」というサービスが創設されたりなど、障がいを持つ方の住まいや働き方の選択の幅を広げることが柱となっています。障害者支援は少しずつではありますが、改正が実施されるごとに整ってきています。
本書では、障害者総合支援法の基本や概要、今回の改正ポイント、サービスの使い方、その他の支援制度について、図解たっぷりで、やさしく解説。専門職として制度について知っておくべき方、サービス事業者、障害者支援員、福祉を勉強する学生さんにとっても、制度の概要や利用方法についてスッキリわかる1冊となっています。
『認知症700万人時代の失敗しない「成年後見」の使い方 第2版』
対人援助の技術・参考書
『対人援助の現場で使える ソーシャルワーク技術』
『対人援助の現場で使える 傾聴する・受けとめる技術 便利帖』
『対人援助の現場で使える 言葉〈以外〉で伝える技術 便利帖』
大切なのは、心理学に基づいたノンバーバル(非言語)・コミュニケーション!
「ちゃんと声をかけたのに」「しっかり説明したのに」相手への声かけや、言葉のやり取りをしっかり行えば大丈夫、と思っていませんか。
自分は言葉を尽くしたつもりでも、全く届いていないことがあります。それは相手が、こちらの話を受け入れる心情になっていないのかも。表情、話し方、身ぶりなどのノンバーバル(非言語)によるメッセージは、ときに言葉以上に強く相手の情動に働きかけます。
本書で紹介している非言語表現についての知識を持てば、日々の相談に効果的に活用するだけでなく、相手側の表現の意味も理解し豊かなコミュニケーションが実現できるようになります。
『対人援助の現場で使える 承認する・勇気づける技術 便利帖』
『対人援助の現場で使える 質問する技術 便利帖』
『本人と支援者が教える!認知症になったあとも「ひとり暮らし・仕事」を続ける方法』
認知症と診断されたけど「まだ働きたい」「自立した生活をおくりたい」方のため工夫とアドバイス!
本書では「認知症と診断されたけど、仕事や自立した生活(ひとり暮らし)を続けたい」と思ったときに、できること・しておくといいことを紹介しています。
カギのかけ忘れ防止/忘れ物対策/スケジュール管理のコツ/自転車や交通機関を使うときの注意点/日用品や食品の在庫管理/主治医とのコミュニケーションのポイントなどの、自立した生活を送るポイント。職場で症状とつきあう方法/会社から理解を得る方法/休職や退職を考えたときにすべきこと/障害者雇用の選択肢などの仕事に関するポイントなど。多くの事例を使い、やさしくアドバイスします。